近年、共働き世代が増加し、企業による両立支援制度の整備が進む一方、制度をうまく活用できていないという声も多く聞かれます。そこで今回、ベビーシッターサービス会社Fluffy Ket代表取締役社長 伊藤梨沙子様と執行役員 田中幸一郎様をお招きし、映像業界での仕事と子育ての両立を考えるトークイベントを開催しました。映像制作現場で活躍するパパママ社員の実体験とベビーシッター活用を通じて、仕事と子育ての両立に必要な制度と風土づくりのヒントを紐解きます。

本トークセッションは、当社映像クリエイティブ事業本部(以下、映クリ)の有志メンバーが中心となり、所属本部員の働き方に関する不安解消を目指す「働き方と未来を考えるプロジェクト」 の一環として開催されました。
トークセッションの冒頭に、映クリ内のアンケートで出産や子育てに踏み切れない理由として「時間の融通が利かない」「成果を出すために、仕事量をこなす必要があり、忙しい」「急なバトンタッチや業務分担が難しい」といった内容が紹介されました。
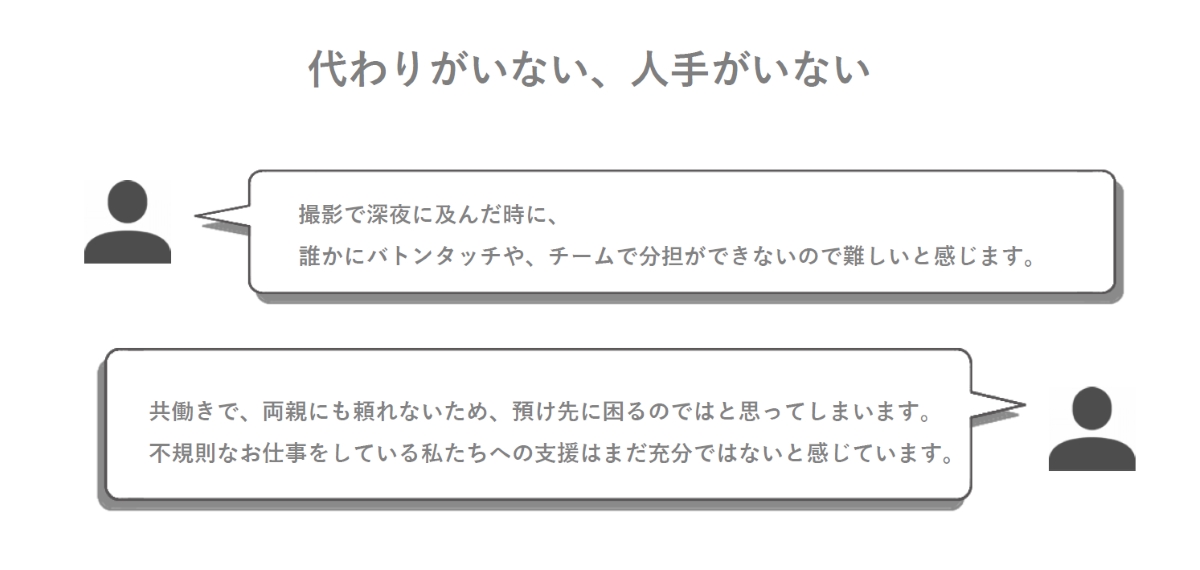
事前アンケート「出産や子育てに踏み切れない理由」より抜粋
映像制作現場での仕事と育児の両立で感じる大変さとやりがい
アンケート結果をふまえ、ママ社員の寺本とパパ社員の永井、和田の3名が仕事と子育ての両立についての実体験を語ります。

寺本:私は2018年に入社してプロダクションマネージャーをしています。 産休育休を経て2024年4月に復職しました。映像制作の現場では深夜や早朝の撮影もありますし、終わり時間がみえない日もある中で、子育てと両立するために試行錯誤の毎日です。子どもの急な発熱でも外せない仕事があれば、周囲の協力を得ながらやりきっています。アンケートにあったような心配事に頷くこともありますが、保育園に預けて離れている分、子どもと一緒にいるのは最高の時間だと感じますし、「子どもと旅行したり、良い思い出を作りたいから仕事を頑張るぞ」というように、子どもの存在が働く上で大きな原動力になっています。

永井:私は2012年に入社してプロデューサーをしています。2024年に子どもが生まれたばかりです。はじめは子どもを愛せるか自信がなかったのですが、生まれてみると「自分の子どもってこんなに可愛いんだ」って常々思います。今は妻が育休を取得していることもあり、これまでと変わりなく仕事することができているのですが、まもなく妻の復職時期が近付いているので、保育園の送り迎えや熱が出たときの対応をどうしていくかを話し合いながら、共働きに向けた準備を進めている状況です。

和田:私は2012年に入社してラインプロデューサーをしながら、2人の子どもを育てていて、共働きです。我が家は夕方のお迎えなど妻が対応してくれているので助かっているのですが、やはり家族の病気で急にどうしても休まないといけないときが大変ですね。私が海外ロケ中に、日本にいる家族全員が体調を崩してしまって、妻から連絡がきた時は、同行していた同僚のプロデューサーはじめ関係者の皆さんに事情を説明して、担当業務を代わってもらったこともあります。

永井:子どもの突然の発熱や体調不良への対応がどうしても解決しないポイントです。今日は病児保育のことも詳しく聞きたいなと思って参加しました。
ベビーシッターについては映クリ内のアンケートでも「前向きに活用したい」という意見が多くありました。一方で「信頼できるベビーシッターに出会うことが難しい」や「深夜や病児保育となると非常に高額になってしまう、そもそも空いていないことが多い」といった活用に踏み切れない声もありました。パパママ社員の3人からもベビーシッターの活用に踏み切れない物理的・精神的なハードルについても具体的な課題が出てきました。

寺本:実はまだベビーシッターを利用したことがないんです。いつも利用している保育園とは全く違う環境で、子どもが不安になっていないかな、泣いていないかな、おむつ大丈夫かな、ご飯食べているかなとか 、仕事に手がつかなくなる気がします。病気の時はなおさら心配です。

永井:うちも一緒。よく分かります。他の人が自分の家の中にいることに対する抵抗感もどうしても拭えないですよね。

寺本:あと世の中から向けられる目、ですね。延長保育は子どもが可哀想だという空気感があったり、ベビーシッターを頼るのは「なんか贅沢だね」という声もあって。映像制作の仕事を続けるためには、仕方ないと思う反面、できることなら自分でやりたい気持ちもあり。そんな葛藤がベビーシッターの活用に一歩を踏み出せない要因になっていると思います。

和田:我が家ではベビーシッター活用を検討したこともありますが、条件が合って空いているシッターさんを探して交渉する、まずここが大変なんです。その上で自分の子どもの特性や家の中のことについて説明も必要で。さらに、子どもが食べるもの、着るもの、遊ぶものを用意して、シッターさんを迎え入れるために家を片付けるなど、意外と時間と労力がかかりそうだったので断念しました。「慣れないことをするより、無理してでも自分たちでやりくりした方がいいんじゃない?」となってしまいます。
専門家から学ぶ!ベビーシッター活用の3つのポイント
今回のトークセッションでは、ベビーシッターサービスを提供するFluffy Ketのお二人より、Fluffy Ketを設立した背景と専門家の立場からベビーシッター活用について3つのポイントを教えていただきました。

伊藤:私は10代の頃から芸能活動を続けてきた中で、皆さんがお話されていたような業界特有の不規則な働き方における子育ての課題を間近で見てきました。働くお父さんお母さんが仕事と子育てを両立しやすくなるお手伝いをしたいという想いがあり、ベビーシッターサービス会社のFluffy Ketを設立しました。

伊藤:私たちの経験をもとに、ベビーシッター活用のポイントをお伝えできればと思います。1つ目は、単発利用ではなく定期的に利用いただくことです。単発利用だとどうしても事前にやり取りする量が増えてしまうため、忙しい状況こそ急な利用ができないという先ほどのお話は理解ができます。また、お子様側もはじめましてのシッターと馴染めるかという不安もあると思います。定期的な利用を重ねていくことによって、親御様ともお子様とも信頼関係を築くことができ、柔軟かつスムーズな対応が可能になるのでおすすめです。
先ほど、病児保育に関するお話もありましたが、私たちの会社にも保育士や看護師の免許を持つ病児保育が可能なシッターが在籍しています。事前面談でお子様のかかりつけの病院等についてもヒアリングを行うため、お預かり中に急な体調変化があった場合は、事前面談の情報をもとに、かかりつけの病院に連れていくなどお子様の安全を第一に対応します。

田中:2つ目は、国や自治体、企業のベビーシッター利用支援制度(※)を活用することです。高い費用がかかるイメージのベビーシッターですが、補助金や支援制度を上手に活用すればリーズナブルにサービスを利用できます。
※当社は、こども家庭庁より「割引券等承認事業主」としての認定を受けており、ベビーシッター利用時の費用負担を軽減するための育児支援制度があります。

伊藤:3つ目は、ベビーシッターをポジティブに活用することです。シッターは保育の経験が豊富ですので、いろんな遊び、かかわり方を知っていますし、私たちのような第三者の大人との関わりあいによって、お子様の社会性や創造性を育むことが期待できます。また、私たちの独自のサービスとして、芸能活動を行うスタッフによる歌やダンスや英語などのエンタメ要素を取り入れた保育を提供しています。ですので、習い事の先生が自宅に来てくれるような感覚でご利用いただくことも良いと思います。このように、ベビーシッターの使い方の幅がたくさんあるということを知ってもらえたら嬉しいです。
「制度」だけでなく、互いに理解し協力し合う「風土」づくりが重要
トークセッションの終盤は、ここまでの話を聞いた感想やみんなが働きやすい「風土」についてシェアする時間となりました。

寺本:今日のトークセッションを通じて、甘えられる先がたくさんあるんだなと思いました。妊娠が分かったときに、「映像制作の仕事を続けながらお母さんをやるんだ!」と心に決めてファイティングポーズをとっていたのですが、そこまで身構えなくても、会社の人が理解を示してくれたりと、みんなが受け入れてくれていると感じており、こうして好きな仕事を続けていられるのかなと思います。仕事と子育ての両立はいろんな大変さも確かにありますが、子どもと会えない時間も無駄じゃないというか、愛情がより増すように感じます。何より子育てが楽しいということを伝えたいです。

和田:私は恥ずかしながら、子どもが生まれる前は「子どもが熱出したから帰ります」と言っていた人に対して「こっちも大変なのに」と思ってしまっていたこともありました。子どもが生まれて初めて気付くこと、理解できたことがたくさんありました。当事者でなくても、仲間の事情に理解し協力し合えるような風土にしていけたらいいなと改めて思いました。
若手の映像制作メンバー代表としてトークセッションに参加した馬場も続きます。

馬場:今日は皆さんのお話を聞いて勉強になることばかりでした。育児は自分にとって遠いことだと思っていたのですが、子どもがいない人も理解を深めていくこと、子育てしやすいような環境にしていくために私たちもできることがたくさんあるなと。新しい当たり前をつくっていく意識を持たないといけないと感じました。
今回のトークセッションを通じて、映像業界における子育てと仕事の両立で感じるやりがいと大変さ、そしてベビーシッターの活用について多くの意見が交わされました。ベビーシッターの活用に対する不安や疑問が共有されたことで今後の活用に対して前向きになったほか、トークセッションをきっかけに、関係者同士の相互理解と協力が深まっていくのではないかという期待の声が多数寄せられました。
最後に、映像クリエイティブ事業本部 茂木本部長より『制度や仕組みも大切ですが、それだけではなく周囲の理解や助け合う風土づくりこそ重要であると「働き方と未来を考えるプロジェクト」の会を重ねるごとに感じます。この取り組みを継続していきましょう』と呼びかけられました。

